こんにちは、リノ(@Lino_EasyLife)です。
キャッシュレスが当たり前になってきた今、
「楽天ペイとPayPay、どっち使えばいいの?」って悩んでる人、結構いると思います。
実際ぼくも、最初はPayPayから入りました。でも楽天ポイントの魅力に気づいて、気がつけば楽天ペイも導入していて。
気づいたら、両方使ってたんですよね。
で、しばらく使ってわかったんです。
「どっちが正解か?」じゃなくて、「どう使い分けるか?」の方がよっぽど大事。
この記事では、楽天ペイとPayPayを両方使っているぼくが、それぞれの特徴と違いを徹底比較したうえで、
どう使い分ければお得に・快適にキャッシュレス生活を送れるか、リアルな視点でまとめました。
目次
楽天ペイとPayPayの基本スペック比較
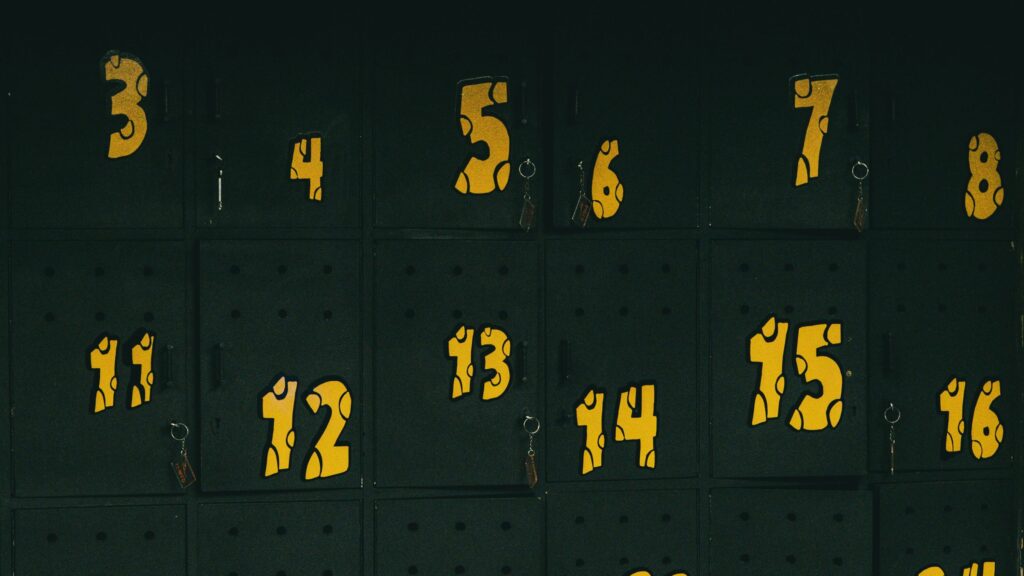
| 項目 | 楽天ペイ | PayPay |
|---|---|---|
| 対応店舗数 | コンビニ・ドラッグストア中心。楽天市場との連携に強みあり | 圧倒的対応数。個人経営の飲食店や地方の店でも対応多数 |
| 還元率 | 通常1.0%(楽天カード払い)+キャンペーンあり | 通常0.5%〜(条件あり)。キャンペーンで高還元もあり |
| 支払い方法 | 楽天カード・楽天キャッシュ・楽天銀行連携 | 銀行口座・PayPayカード・ソフトバンク系との親和性◎ |
| ポイント | 楽天ポイントが貯まる・使える | PayPayポイントが貯まる・使える(LINEポイント連携あり) |
| UI/使いやすさ | 画面がシンプルで直感的。支払いもワンタップで完了し、初心者でも迷いにくい。広告も少なめ。楽天ポイント獲得やキャンペーンへの導線も整理されていて、楽天経済圏のポータル的役割もあり。 | 多機能だがやや複雑。広告や通知が多く、クーポンの事前獲得が必要な点は少し手間。ぼく自身、やることが多くて忘れることもよくあります。 |
| キャンペーン | 常時系のポイント還元が多く、楽天経済圏との相性が抜群 | 抽選・全額キャッシュバックなどド派手なキャンペーン多数。実際に当たったこともあり◎ |
実際に使って感じた「楽天ペイとPayPayの違い」

① ポイントの貯まり方が全然ちがう
- 楽天ペイは地道で安定タイプ
日常の支払いでじわじわポイントが貯まる。楽天カード連携で常時1%以上の還元。 - PayPayは爆発力型
通常還元は低めでも、キャンペーンの波に乗れば全額還元なんてことも。
ぼくも一度、ランチ代がまるごと返ってきたことがあります。
② 店舗対応の“広さ”がちがう
- PayPayは対応店の網羅性が異常
個人経営の店、屋台、地方の観光地、移動販売車まで対応していることが多く、“どこでも使える感”が段違い。現金なしで出歩くならPayPayは必須。 - 楽天ペイは都市部&チェーンに強い
コンビニやドラッグストアでは安定の対応。楽天ポイントを使える飲食チェーンも増えているが、ローカルな個人店では対応していないことも多い。
③ アプリの使いやすさは「性格」で選べる
- 楽天ペイ:シンプルだけど楽天経済圏の玄関口
決済・履歴確認に集中でき、UIもすっきり。楽天ポイント獲得や連携サービスにもすぐアクセスできて、“使いやすいポータルアプリ”としての完成度が高い。 - PayPay:高機能だけど情報過多気味
機能が多くて便利だけど、通知・広告・スタンプ・ミッションなどやることが多く、ぼくもよく「忘れてた…」ってなります。慣れれば強いが最初は手こずるかも。
楽天ペイとPayPay、こう使い分けるのが正解!
1. コンビニ・ドラッグストアでは楽天ペイ
- 楽天カード連携で常時1%以上の還元+楽天ポイントも使えて、日常使いの“安定お得枠”として強い
2. 地元の飲食店・個人店ではPayPay
- 「PayPayだけ対応」してる小規模店は本当に多い。現金不要生活をしたい人にはマスト
3. キャンペーン狙いならPayPayに寄せる
- 還元率の爆発力はPayPay。一撃で全額戻ることもある(←ぼくも経験済み)
4. ネット系サービスや楽天市場なら楽天ペイ
- 楽天サービス内での還元強化・SPU条件達成に貢献。ネット決済とポイント活用の相性◎
まとめ:キャッシュレスは“どっちか”じゃなくて“両方”が正解

楽天ペイとPayPayは、それぞれ得意分野が違う。
だからこそ、「選ぶ」より「場面で使い分ける」方が、実際の生活ではよっぽど得になります。
最適な使い方はこれ!
- 日常の支払い → 楽天ペイでコツコツ貯める
- 小さなお店や旅行先 → PayPayで柔軟に対応
- キャンペーンの波が来たら → PayPayでぶん回す
- 楽天市場・楽天系サービス → 楽天ペイで還元底上げ
最初はどっちを選べばいいか悩んでたぼくも、
今ではこう言ってます。
「両方使えば、全部拾える。」
ぜひ、あなたの生活にも“お得の使い分け”を取り入れてみてください!











