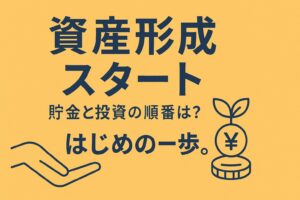こんにちは、リノ(@Lino_EasyLife)です。
「気づいたら給料日前にはいつもカツカツ…」
「頑張って節約してるのに、なぜかお金が貯まらない」
そんな人にこそ試してほしい、“仕組みで黒字をつくる”3つのステップをまとめました。
月5万円の余裕が生まれれば、将来への不安がぐっと減って、投資や副収入の種まきも始められます。
まず「黒字家計=仕組み」だと知る

家計が赤字になる原因って、実は“気合不足”や“節約意識の低さ”ではありません。
本当に必要なのは、「仕組みで黒字になる流れ」をつくること。
モチベーションのように何か周囲の環境に影響されてしまうようなものに頼ってしまうと、そのものがなくなった時に困るのであくまで”自動で”貯まるようにしています。
- 支出を自動で減らす仕組み(定額支出・見直し)
- 収入を自動で増やす仕組み(副業・ポイント)
- 貯蓄・投資を自動で続ける仕組み(自動積立・予算振り分け)
この記事では、ぼくが実際にこの仕組みを使って、月5万円の黒字化を実現したロードマップを解説していきます。
Step 1|支出を減らす:固定費を見直して月2~3万円浮かせる
支出改善は、固定費からやるのが圧倒的に効率的です。
家計簿はざっくりでOK:
「月に何がいくら出てるか」を大雑把に掴むだけでも十分。
分ける項目は家賃・スマホ代・電気代といった固定費以外には食費と日用品とその他くらいのザクザクでOK
固定費は一度の見直しで減らせますが毎月の食費などは大きく変動してしまうので最初はあまり気にしない方が長続き(=節約に直結)します。
頑張れる!という人は「食料品」と「外食費」を分けておくと自分の消費傾向が分かっていいですよ。
見直しやすい固定費TOP3:
① スマホ料金(→楽天モバイルに変更)
② 保険(不要な民間保険は解約)
③ サブスク(使ってないサービスの整理)
ぼくは楽天モバイル+楽天Turboに変えただけで、月8,000円以上カットできました。
固定費削減のプロセスを記事にまとめてあるので併せて読んでみてください。

保険に関しては自分が必要だと思っているより入りすぎている人が多いように思います。
以前のぼくもそうで、不安からたくさんの保険を契約していましたが、実際に自分や家族にどれだけの金額があれば病気や事故に遭った後に過ごしていけるか計算したら意外と少ない保険で大丈夫なことがわかりました。
サブスクは家計簿アプリを入れるなどして月々眺めていると、知らない名称の引き落としが見つかったりします。
例えば年に一度も使わなかったら会費が発生するクレカなどじわじわと資産を削るものを除いていきましょう。
さらに、以下のような固定費見直しチェックリストを使うと、一気に全体が見えてきます。
- 通信費(スマホ/ネット)
- 保険(医療・がん・学資)
- サブスク(動画/音楽/雑誌)
- 水道光熱費(プラン見直し/契約切替)
- 銀行・ATM手数料
Step 1.5|食費・飲み会代を“我慢せず”にコントロールするコツ

「食費や飲み会代って気づいたらかなり出てる…」
ぼく自身も、最初に家計を見直した時に驚いたのがここでした。
でも、“無理に我慢”する節約って、正直しんどいんですよね。
食費は「パターン化」と「疲れてる日の逃げ道」の2つがカギ
ぼくが始めたパターン化がこちら。
- 週1まとめ買い+冷凍保存で、食材ロスと外食が激減
- お昼ごはんはスープジャー生活にしたら、飽きずに続いた
- コンビニ断ちは無理だったので「週2までOKルール」にした
“節約は感情との戦い”だから、100点を目指すと挫折します。
大切なのは「疲れてる日でも最低限守れる設計」にすること。
自炊するとめちゃくちゃ食費は浮きますが急に始めるとどこかで限界がきちゃいます、スロースタート&低燃費の継続が強いです。
飲み会代は「行く/行かない」より「予算と頻度のルール化」
- 飲み会は月1〜2回だけ“楽しむ会”と決めて、他は断る勇気
- 「2軒目は行かない」「1時間で切り上げる」も効果的でした
- 「飲んだら翌日は外食(Uberでも)禁止」というルールも入れた
まったく飲み会に行かないというのはなかなか難しいもの。
“制約と誓約”で機会を限定すると参加した飲み会が何倍も楽しいというオマケもありました。
ご褒美制度を導入してみたら、逆に貯まった話
「月に貯めた額の1/3は、自分のために使っていい」ってルールを作ったら、節約のストレスが激減しました。
不思議なことに、安心感があることで逆に無駄遣いも減ったんです。
そしてそのうち、「ご褒美で何買おうかな」って考えてるうちに、
本やスキル講座、ガジェットなど“自己投資”に変化していきました。
節約=我慢ではなく、節約=選択肢の整理と考えましょう。
Step 2|収入を増やす:フリマアプリ・ポイ活・副業で月2万円稼ぐ
支出カットだけでは限界があります。ここからは「増やす側」の戦略です。
おすすめはフリマアプリ、ポイ活、副業とみなさんも聞いたことのあるものばかりだと思います。
始める順番はフリマアプリ >> ポイ活 > 副業 がいいかと思います。
なぜその順番なのか解説しますね。
フリマアプリで不用品販売
フリマアプリからがいいのは以下の3つから。
- ものが減って綺麗な部屋になる
- メルカリやラクマで、月1万円以上は現実的
- 「これ売れるの?」って思ったモノほど売れたりします
綺麗な部屋だと考えもまとまりやすいですし何かを思いついても物を探す時間が圧倒的に少なくて済むからです。
人が物を探す時間は平均で1日13.5分から20分程度と言われ年間で54時間から80時間!
これに自分の時給をかけると…ゾッとしませんか?
メルカリやラクマってそこまで売れなんじゃ…とぼくも思っていましたが、
引っ越しをきっかけに売り出してみたらなんと12万円にもなってびっくり。

売ったものといっても来シーズンは着ないだろうなと思っていたジャケットや使わなくなったキャンプ用品などなど。
実のところ、結構な金額で買ってしまったから捨てるに捨てられず…みたいなものばかりw
年季が入ったものもあったので売れるか心配でしたが、出品してみるとバンバン売れていきました。
ポイ活で月3000~5000円

楽天経済圏に入れば、買い物するだけでどんどん貯まると分かったのがつい2年前。
欲しい食材やガジェットがあったら楽天市場でカートに入れておいて「お買い物マラソン」か「0と5が付く日ポイント5倍DAY」で購入しただけ。
楽天モバイルにしておけばもっとポイント効率が上がりますが、他社スマホを利用していても楽天で買い物するだけなのでもっと早く始めておけばよかったです。
顔出し不要の副業を選ぶ
副業や発信って聞くと、「顔を出してYouTubeとかやるの?」と思う方もいるかもしれません。
でも、ぼく自身がやってきた中で感じたのは、顔出ししない働き方こそ、むしろ続けやすいということ。
特にこんなメリットがあります。
- 本業や家族にバレずにできる
副業NGの職場でも安心。知り合いに見つかるリスクを抑えられます。 - 炎上や身バレの不安がない
ネットに顔を出すと、写真が勝手に使われることも…。顔出しなしなら、こうしたリスクも回避できます。 - 「見られてる感」がないから気がラク
顔を出してると「表情どうしよう」「身なり大丈夫かな」と気になって、疲れてしまうことも。顔出しなしだと、気負わずに続けられます。 - 外見に左右されず、中身で勝負できる
文章力やアイデア、情報の価値で勝負したい人にとっては、むしろ顔出ししない方が集中できます。 - キャラクターやペンネームで“別の自分”を作れる
顔出ししないからこそ、自分らしい世界観を自由に演出できます。たとえばぼくのように「リノ」みたいな名前で発信するのもその一つ。
つまり、「顔を出す勇気がないから副業は無理」と思っていた人こそ、実はかなり相性がいいのが“顔出ししない副業”なんです。
ブログ、フリマ、スキル販売、音声配信、LINEスタンプなど…。
やってみると分かりますが、自分を出さなくても価値を届ける手段はたくさんあります。
Step 3|仕組みに落とし込む:黒字をキープするための9つのチェックリスト

家計が黒字になったら、次は“それを維持する仕組み”を整える段階です。
「また元に戻ってしまった…」とならないように、以下の9ステップで“自動的に貯まる家計”をつくっていきましょう。
1. 給料日の自動振替を設定する
→ 毎月の給料日に、自動で貯蓄用口座にお金を移す仕組みをつくります。
推奨配分(手取り20〜25万なら)
先取り貯蓄:2〜3万円
固定費+変動費:残りを口座に残す
(ネット銀行の定額振替機能がおすすめ)
2. つみたてNISAや投資信託の自動買付を設定
→ “残ったら投資”ではなく、“自動的に先取り投資”。
少額でもOK。まずは月3,000円からでも十分です。
3. 「生活費」と「遊び費」の予算を月初に決めておく
→ 自由に使っていいお金(ご褒美枠)をあえて用意すると、ストレスも浪費も減ります。
枠があるとそれに合わせてしまう習性を利用しています。
4. 家計簿アプリ(MoneytreeやマネーフォワードME)を連携
→ 自動で入出金が記録され、毎月の流れが“見える化”されます。三日坊主でも大丈夫。
5. 週1回、支出の振り返りタイムを設ける
→ 金曜の夜や日曜の朝に3分でOK。「今週どうだった?」と確認するだけで改善が始まります。
Googleカレンダーやリマインダー登録をしておくと忘れないので今!設定しちゃいましょう。
6. ご褒美ルールを決めておく(例:貯めた額の1/3は自由に使える)
→ 我慢だけの節約は続かない。自分への還元があるとモチベーションが保てます。
7. 毎月1日は「家計メンテナンスデー」にする
→ 先取り振替、アプリチェック、予算振り直しを一括で実施。月1回のルーチン化がカギ。
マネーフォワードなら予算項目があるので見直しも簡単でした。
8. 家計サイクルをGoogleカレンダーに登録
→ 生活リズムの中に“お金の習慣”を入れることで、仕組みが自然に機能します。
9. 月末は「ご褒美デー」として予定を入れる
→ 節約の達成感を味わえる日をちゃんと確保する。メリハリがある方が長く続きます。
仕組みを決めるポイント
節約も貯蓄も、がんばりすぎると続きません。
大事なのは「がんばらなくても自然と黒字になる仕組み」を作ること。
この9つのステップを整えれば、お金の悩みはグッと軽くなります。
ぜひ今日から1つずつ、ゆるく始めてみてくださいね。
家計シミュレーション(例)
- 収入:手取り23万円
- 固定費:11万円(通信・保険・家賃など)
- 変動費:5万円(食費・雑費・交際費)
- 先取り貯蓄:3万円
- 副収入:+2万円(フリマ+ポイ活)
- → 最終黒字:+6万円
🧭 よくある質問へのぼくなりの回答(FAQ)
というわけで|「気合」ではなく「仕組み」で黒字をつくろう

家計の黒字化は、気合や根性に頼るものではありません。
仕組みを整えれば、誰でも“自然にお金が残る”状態をつくれます。
今回紹介したステップをもう一度おさらいすると、
- 固定費を見直して、支出を減らす
- 副業やポイ活で、収入を増やす
- 先取り貯蓄や自動化で、仕組みに落とし込む
この3ステップをベースにすれば、月5万円の黒字は無理なく実現可能です。
そして何より大事なのは、「ちゃんと使うから、ちゃんと残る」という考え方。
節約=我慢ではなく、人生に余裕を取り戻す手段としての仕組みづくり。
「毎月ちょっとずつ貯まる」ことが、未来の自分にとっていちばんの安心になります。
まずは今日、スマホ料金やサブスクの見直しから始めてみませんか?